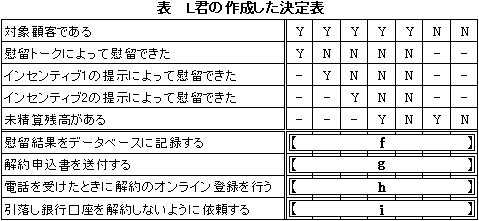| ■問6■ |
|
コールセンタ業務の改善に関する次の記述を読んで,設問1~4に答えよ。
クレジットカード会社のコールセンタに勤務するL君は,クレジットカード(以下,カードという)の優良顧客の解約防止と解約手続の効率化について検討するよう指示を受け,現在の業務について調べた。
|
コールセンタのオペレータは,顧客からのカード解約申出の電話を受けると,解約申込書を送付するので,裁断したカードと所定事項を記入した解約申込書を一緒に返送するように依頼する。併せて,その顧客のカード利用の精算状況をオンライン照会で調べ,未精算残高がある場合は,引落し銀行口座を解約しないように依頼する。
L君は,すべての顧客に対し同じ扱いをしている現在のやり方に疑問をもった。そこで,優良顧客の解約申出に対しては,電話を受けた時点で慰留することにし,さらに,解約業務自体の合理化ができないか検討した。 |
|
|
■設問1■
|
L君は上司のNさんに,オペレータが解約申出の電話を受けたときに,その顧客が当社にとって大切な顧客か否か判別する方法について相談した。相談内容に関する次の記述中の
【 】
に入れる適切な字句を,解答群の中から選べ。
| Nさん |
「 |
まず,顧客の利用データを分析してみよう。様々な観点からの分析が必要だが,最初から複雑な分析を試みるとなかなか進展しないので,収益が利用金額に依存することに着目してみよう。」 |
| L君 |
「 |
顧客を判別するために,カード保有期間が1年以上の顧客を対象にグラフを二つ作ってみました。一つは過去1年間の利用回数と,1回当たりの平均利用金額のグラフ(図1),もう一つは保有期間と,過去1年間の累積利用金額のグラフ(図2)です。
図1を見ると 【 a 】
の領域の顧客に対しては解約を慰留し,【 b 】
の領域の顧客に対しては慰留の必要がないと思いますが,【 c 】
の領域の顧客については判断できません。」 |
| Nさん |
「 |
図1の 【 c 】
の領域の顧客については,利用回数が少ない,あるいは利用金額が小さい,ということだけでは判断できないと思う。図2ではカードの利用による収益が利用金額に依存することから,【 d 】
と 【 e 】
の領域の顧客を,解約を慰留する対象としよう。」 |
| L君 |
「 |
では,図1の 【 a 】 と 【 c 】
の領域の顧客のうち,図2の 【 d 】 と 【 e 】
の領域にも含まれる顧客を,解約を慰留する対象として全体の流れを検討してみます。」 |

| ア Ⅰ |
イ ⅠとⅢ |
ウ Ⅱ |
エ ⅡとⅣ |
オ Ⅲ |
カ Ⅳ |
| ア α |
イ α と γ |
ウ β |
エ β と δ |
オ γ |
カ δ |
|
|
■設問2■
|
L君は,解約申出の電話を受けたオペレータの対応手順案を検討し,決定表(表)にまとめた。表中の
【 】
に入れる適切な字句を,解答群の中から選べ。
| (1) |
解約申出の電話を受けたオペレータは,オンライン照会画面に会員番号を入力し,慰留対象の顧客(以下,対象顧客という)かどうかの判別と精算状況を調べる。 |
| (2) |
対象顧客の場合には,次の手順を展開して,慰留経過及び結果をデータベースに記録する。 |
| ① |
あらかじめ準備した,解約を慰留する会話(以下,慰留トークという)を展開する。 |
| ② |
慰留トークによって対象顧客が解約を取りやめた場合,記録して電話を切る。 |
| ③ |
慰留トークでも対象顧客が解約を取りやめない場合は,解約引止め策としてギフトカードの贈呈(以下,インセンティブ1という)を申し出る。インセンティブ1によって対象顧客が解約を取りやめた場合,記録して電話を切る。 |
| ④ |
インセンティブ1の提示で,対象顧客が解約を取りやめない場合には,インセンディブ1の代わりに,年会費の無料化(以下,インセンティブ2という)を申し出る。インセンティブ2によって対象顧客が解約を取りやめた場合,記録して電話を切る。 |
| ⑤ |
インセンティブ1,2を提示しても,対象顧客が解約を取りやめない場合には,解約申込書を送付するので,裁断したカードと所定事項を記入した解約申込書を一緒に返送するように依頼し,記録して電話を切る。このとき,未精算残高がある場合は,引落し銀行口座を解約しないように併せて依頼する。
後日,解約申込書が到着したとき,解約のオンライン登録を行う。 |
| (3) |
対象顧客でない場合は,未精算残高がなければ,解約のオンライン登録を行い,カードを裁断し廃棄するように依頼する。未精算残高があれば,引落し銀行口座を解約しないように依頼した上で,解約のオンライン登録を行い,カードを裁断し廃棄するように依頼する。 |
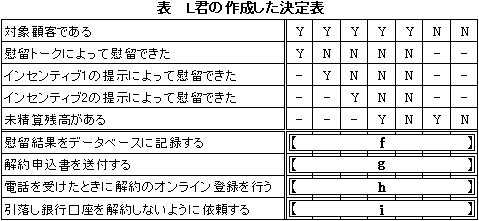
解答群

|
|
■設問3■
|
L君は,この検討結果を実施する際の収支について試算することにした。試算方法に関する次の記述中の
【 】
に入れる適切な字句を,解答群の中から選べ。
| (1) |
1年間の解約申出顧客総数を[申出総数]と表す。 |
| (2) |
[申出総数]に対する対象顧客の比率を[対象比率]と表す。 |
| (3) |
対象顧客から得ている年間平均収益を[対象収益]と表す。 |
| (4) |
解約を申し出た対象顧客のうち,インセンティブ1によって解約を慰留できる割合を[慰留確率1]と表す。 |
| (5) |
解約を申し出た対象顧客のうち,インセンティブ2によって解約を慰留できる割合を[慰留確率2]と表す。 |
| (6) |
インセンティブ1に必要な1顧客当たりの費用を[コスト1]と表す。 |
| (7) |
インセンティブ2に必要な1顧客当たりの費用を[コスト2]と表す。 |
| 費用
1 |
: |
1年間のインセンティブ1の費用合計額は,【 j 】
によって算出する。 |
| 費用
2 |
: |
1年間のインセンティブ2の費用合計額は,【 k 】
によって算出する。 |
| 効 果 |
: |
1年間にインセンティブ1,2の提示によって解約を慰留できた対象顧客から得られる年間収益合計額は,【 ℓ 】
によって算出する。 |
| 収 支 |
: |
効果-(費用1+費用2)によって算出する。 |
| ア |
[慰留確率1]×[コスト1]+[慰留確率2]×[コスト2] |
| イ |
[申出総数]×[対象比率]×[慰留確率1]×[コスト1] |
| ウ |
[申出総数]×[対象比率]×[慰留確率2]×[コスト2] |
| エ |
[申出総数」/[対象比率]×[慰留確率1]×[コスト1] |
| オ |
[中出総数」/[対象比率]×[慰留確率2]×[コスト2] |
| カ |
[申出総数]×[対象比率]×([慰留確率1]+[慰留確率2])×[対象収益] |
| キ |
[申出総数]×[対象比率]×(1-([慰留確率1]+[慰留確率2]))×[対象収益] |
|
|
■設問4■
|
L君はここまでの検討結果をNさんに報告した。次の記述中の
【 】
に入れる適切な字句を,解答群の中から選べ。
| L君 |
「 |
これから詳細に検討しなければならない項目について,幾つか疑問に思ったことがあります。収支計算をする場合,インセンティブによる慰留確率とコストについてどのように決めたらよいのか分からず困っています。」 |
| Nさん |
「 |
慰留の対象顧客を絞り込み,様々なパターンを実験的に実施し,その結果を参考に決めることにしてはどうだろう。」 |
|
L君 |
「 |
どうしてですか?」 |
|
Nさん |
「 |
今回のケースに限らず新しい対策を実行するときには,すべての条件が明確に定まらないことが多い。そんなときに,全顧客を対象にするとリスクも大きいので,一部分の顧客を対象に対策をスタートさせる工夫が必要だろう。」 |
|
L君 |
「 |
次に不安に思ったのは,インセンティブが欲しくて何度も解約を申し出てくるケースです。」 |
|
Nさん |
「 |
実際の運用を始めると検討段階では想定していないケースが発生すると思うよ。発生する可能性のあるすべてのケースを事前に洗い出すことは難しいので,十分に検討した段階で,ある
【 m 】
の上で運用をスタートすることが肝心だろう。実際に運用し,当初の
【 m 】
が正しいか検証し,更にその精度を向上させたり,新しい
【 m 】
を追加することがより良い結果をもたらすので,スタート前から心配しすぎる必要はないと思う。
L君が心配するケースに関しては,オペレータが顧客と交わした会話の内容をコンパクトにまとめ,データベースに登録することが大切だ。顧客との会話の履歴を全オペレータが
【 n 】
できる仕組みを作れば,顧客からの不自然な申出はある程度防げると思う。大切なことは,あらかじめ準備した慰留トークをベースにオペレータが顧客の要望に合わせて会話をし,解約を慰留するだけでなく,解約申出の理由や,解約申出までの経緯を聞き出すことだ。
当初はオペレータ一人一人の 【 o 】
に依存するのは仕方がないと思うけど,各オペレータの会話を蓄積し,慰留に成功したケースや失敗したケースを分析して慰留トークをレベルアップさせ,個人のノウハウを全体で有効に使えるようになるといいね。」 |
| ア CRM |
イ 仮説 |
ウ 関係 |
エ 共有 |
| オ 資格 |
カ スキル |
キ 占有 |
ク データベース |
| ケ 認証 |
|
|
|
|
|
■答え■
|
| 設問1 : |
a-ア,b-オ,c-エ,d-ア*,e-ウ* (*d,e
は順不同 ) |
| 設問2 : |
f-ア,g-エ,h-キ,i-オ |
| 設問3 : |
j-イ,k-ウ,ℓ-カ |
| 設問4 : |
m-イ,n-エ,o-カ |
|
|
|